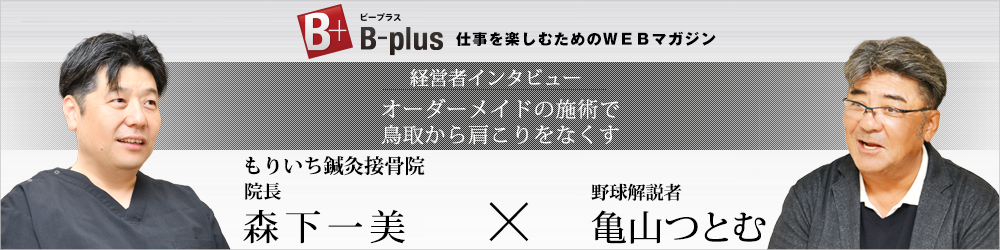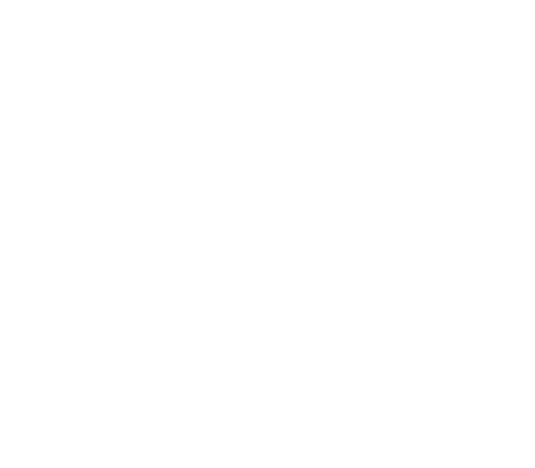自分の
カラダを知る
"だから"改善する


お知らせNews
お客様にも学んでもらう
新しい時代を見据えた整体院です
「原因不明」
病院に行っても、こう言われてしまう。
接骨院に行ってみるも、一時的に楽になった気がするけど
しばらくするとまた痛みが出てくる
もりいち整体院は、そんな慢性的な痛みを
根本から改善することを目指しています。
根本改善できる理由Why you succeed
もりいち鍼灸接骨・整体院で根本改善を達成できる理由
それは「お客様自身に身体への感性を高めてもらう」ということを重視しているから。
「原因の解明」→「施術で身体を緩める」→「習慣改善のためのセルフケア」→「多面的な相談対応」という、一時的に痛みをとるためではなく、身体を根本から改善するために目的を明確化した施術をします。

独自メソッドにより本当の原因を発見
本当の原因とは「どのような歪みが生じているのか」という目で見てすぐ分かる部分と「どのような生活習慣がその歪みを生じさせたのか」という部分の2つ。痛みを根本から改善するために重要なのは後者。原因は意外な所にあります。

歪みを取り除く、施術
カラダの歪みと痛みの本当の原因について、おおよその推測がついたら、まずは痛みを軽減するために筋膜リリースや鍼などの各種手技を用いてカラダの緊張を解いていきます。

カラダを理想的な状態へと導く、あなただけのセルフケア
どの部位の筋肉が硬いのか。どのようなカラダの使い方のクセがあるのか。それらを見極めることができる当院だからこそ、あなたにとって最適でムダのないセルフケアを提供できます。

睡眠・無料相談対応
せっかく素晴らしいトレーニングをしているのに、睡眠バランスが崩れていたりすると逆に体調を崩したり怪我をしたりすることもあります。そのようなことを防ぐために、睡眠などのご相談もいたしております。(ZOOM無料相談)
その他others
割引や回数券情報については、もりいち公式LINEにて告知および提供をしています。
カラダの痛みに関するお役立ち情報も発信しますので、よかったらどうぞ。
施術の流れFlow
施術の流れは以下のとおりになります。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

- 1.仮予約
- システムより仮予約後、確定したらもりいち鍼灸接骨院・整体院へお越しください。(施術中は電話に出られないことがあります。その際はコチラから携帯電話(090-5709-9532)で折り返しますのでご了承下さい。)

- 2.タブレット入力
- 今のカラダの状態、いつからその状態で苦しんでおられるのかなどを専用のタブレットに入力いただきます。ほんの些細な事でもお書きいただいて結構です。

- 3.カウンセリング
- 入力情報をもとに、カラダの状態や悩みをさらに詳しくお聞きしていきます。一見すると痛みとは関係なさそうなことでも、お気軽にお話しください。

- 4.状態チェック
- 痛みや不調の原因となっている個所を発見し、あなたのカラダの状態に合った施術プランを提案させていただきます。

- 5.施術
- 実際に施術を開始していきます。慰安目的ではなく、しっかりとカラダをより良い状態にしていくことを心がけます。

- 6.セルフケア伝授
- オーダーメイドのセルフケアをお伝えします。今後のメンテナンスと自宅での過ごし方をアドバイスしたのち、ご帰宅となります。

 TEL予約
TEL予約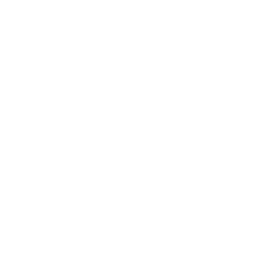 LINE予約
LINE予約